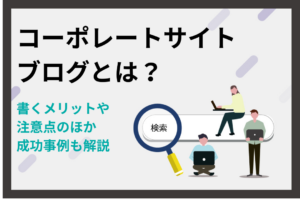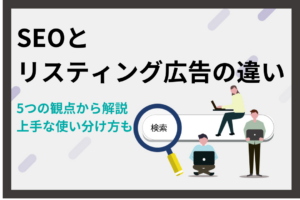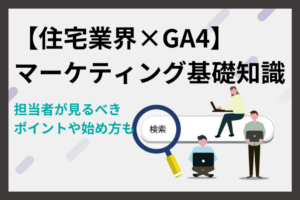-
集客に強いホームページ
-
グラフィックデザイン
グラフィックデザイン -
LINE社認定パートナー事業
-
その他サービス
-
会社案内
-
採用・パートナー募集

SEO対策とはホームページへの流入を増やし、自社の認知向上や集客力強化を図る施策です。
潜在層から顕在層まで幅広くアプローチできるうえ、中長期的に見ると費用対効果が大きく優れている点がメリットになります。
しかし、ノウハウが不十分なまま、やみくもに取り組んでも効果を発揮しません。
特に、制作の軸となる「ある工程」をしっかり押さえないことには、たとえ質の高いコンテンツを完成させても、ユーザーの目に触れる機会は少なくなってしまいます。
この記事では弊社の代表取締役「澤田 将司(以下:澤田)」とSEO戦略事業部チームリーダー「加藤 信之(以下:加藤)」の対談をもとに、SEO対策で最も重要な工程とは何か、近年におけるSEOの傾向とともに解説します。
コンバージョン率を伸ばすノウハウや、AI時代でも効果を発揮するSEO対策のコツもあわせて紹介するので、ぜひ参考にしてください。
目次
弊社のSEO支援でアクセス数が確実に伸びる理由

弊社がSEO対策を支援している企業さんは、アクセス数が伸びているところがほとんどですよね。
そうですね。
アクセス後のコンバージョンはクライアントによるものの、セッション数は基本的に右肩上がりで伸びています。
確実にアクセス数が増える理由は、どこにあるのでしょうか。
キーワード選定を最重要視している点かなと思います。
クライアントのホームページや商材など現状を見たうえで、勝てるキーワードに優先順位をつけて対策するという形がうまくいっていると感じています。
もちろん、キーワード選定後の構成作成や執筆も大切です。
しかし、キーワード選定でつまずいてしまうと、そのあとどれほど良いものを作っても、上位表示できません。
キーワード選定を間違えてしまうと、間違った努力に時間を費やしてしまうということですね。
そうですね。
そのため、キーワード選定はかなり慎重に行っています。
アクセス数の調べ方や成功事例について知りたい方は、こちらの記事もあわせてチェックしてみてください。
【関連記事】自社・他社ホームページにおけるアクセス数の調べ方|運用効果を上げた事例も紹介
SEOのキーワード選定について

SEOのキーワード選定について、以下の3つを解説します。
- 押さえたい3つの要素
- 具体的な選定ステップ
- 上位表示されやすいキーワード群の構成
それぞれ詳しく見ていきましょう。
押さえたい3つの要素
SEO対策のキーワード選定で押さえておきたい要素は、以下の3つです。
- 検索ボリューム
- コンバージョンまでの近さ
- クライアントの状況(ドメインパワー※や扱う商材など)
※検索エンジンからの評価を数値化したものであり、高くなるほど上位表示されやすくなる
キーワード選定では、上記3つが重なる絶妙なところを狙います。
より具体的に言うと、以下のようなキーワードになります。
- 検索ボリュームがそこそこある
- 上位表示されたときにコンバージョンにつながる
- 競合のホームページに対して相対的に勝てる
検索ボリュームが多ければ多いほど良いといった、単純なものではないのですね。
もちろん、多いに越したことはないものの、クライアントの商品を買ったり問い合わせが増えたりなど、コンバージョンにつながる可能性がないと意味がありません。
かつ、「検索上の競合他社に勝てるか」も考えないといけないという感じですね。
そうですね。
実はキーワード選定については一時期、社外のパートナーさんに外部委託することも考えました。
しかし、毎月の定例会議や日々のコミュニケーションでやり取りしている社内の担当者のほうが、上記で紹介した「絶妙なキーワード」を見つけやすいと感じました。
そのため、現在もベイス内でキーワード選定を行っています。
具体的な選定ステップ
まずは、クライアントの商材に関するキーワードをすべて洗い出すことが大切かなと思いますが、それはツールを使えば誰でもできます。
そのあとが、先ほど話にあった3つの要素でフィルターをかける工程になるということですよね。
そうですね。
第1のフィルターとして検索ボリュームを見て、第2のフィルターで「そのキーワードで上位表示とっても、うちの商品売れないよね」というものを除外していく流れになると思います。
このあたりで、数千・数万とあったキーワードが数百程度に削ぎ落されます。
最後に第3のフィルターとして、ドメインパワーなどを見て上位表示の可能性を判断すると、トップ100ほどのキーワードが残るイメージでしょうか。
その通りです。
最終的に「検索ボリュームがあり、コンバージョンまで近く、自社で勝てる」という期待値が一番高いキーワードから、優先順位を付けて対策していく形となります。
上位表示されやすいキーワード群の構成
SEO業界では、「メイントピックとサブトピックがツリー状(三角形)になっているほうが、SEO上で強い」とよく言われます。
対策していく順番としては、優先順位に沿って上から下まで順番に進めるよりも、やはりツリー状が望ましいのでしょうか。
そうですね。
1個のキーワードよりも、それに連なるサジェストキーワードや関連キーワードも洗い出して、1つの三角形として塊で対策していく方が上位表示しやすいと言われてます。
例えば、「クレジットカード おすすめ」というメイントピックがあったら、「クレジットカード おすすめ 10代」「クレジットカード おすすめ 20代」などのサブトピックをぶら下げていくということですね。
専門会社と世間とでは「SEO対策」の認識にズレがある?

加藤さんから見て、「自分の肌感と違うな」と思うSEO対策のトピックはありますか。
オリジナル情報やE-E-A-T(※)の重要性について、SEOに携わっていない方にはまだまだ広がっていないなと感じています。
※Googleの評価基準である「Experience(経験)」「Expertise(専門性)」「Authoritativeness(権威性)」「Trustworthiness(信頼性)」の頭文字を取ったもの
「SEOといえば、何かしらの裏技を使って対策していく」という数十年前のイメージを持っている方が少なくありません。
とはいえ、そのような裏技的な方法は、Googleのコアアップデート(※)ごとに検索順位が沈んでいきます。
※検索アルゴリズムの改善を目的とした更新
真面目にやっているSEOの会社ではオリジナル情報やE-E-A-Tを重視している一方で、世間ではまだ裏技的SEOを信じているという意識のギャップがあると思います。
逆に言うと、裏技をちらつかせるようなSEO業者には要注意ということですね。
コンバージョン率が上がる企業・上がらない企業の違い

ホームページの流入数が増加したからといって、コンバージョン率が改善するとは限りません。
ここでは、コンバージョン率が上がる企業・上がらない企業の違いとして、以下の2つを解説します。
- 商材力とページ構成
- 導線のデザイン
それぞれ詳しく見ていきましょう。
違い①:商材力とページ構成
コンバージョン率については、「商材がそもそも競合に勝てるものなのか」「ターゲットページの見せ方に課題はないか」という視点でまず見る必要があります。
対策したキーワードで流入してきたユーザーと、売りたい商品がミスマッチするケースもありそうです。
そうですね。
そもそも連れてきている人が間違っている可能性と、遷移させたあとのページに問題がある可能性、この2つがコンバージョンにつながらない要因として考えられます。
違い②:導線のデザイン
細かく見るとブログ記事からターゲットページへの誘導方法、いわゆる「導線のデザイン」もコンバージョン率に関わってきますよね。
その通りです。
導線では、次項で紹介するポップアップバナーが効果的です。
また、本文に馴染む形で、以下のような場所にターゲットページのリンクを入れることも重要です。
- ユーザー維持率が高い目次
- アテンションが高い本文中
- 記事の下 など
このようにコンバージョン率を上げる導線の最適解はテンプレート化されているので、それらをきちんとできているか見直すことが大切だと思います。
コンバージョンへつなげるポップアップバナーのコツ

コンバージョンへつなげるポップアップバナー(※)のコツとして、以下の2つを解説します。
※Webページを閲覧しているとき、画面右下などに突如表示されるバナー
- デスクトップ用サイト(PC版サイト)では必ず入れる
- 引きの強い訴求を盛り込む
ホームページ全体の導線設計や成功事例について知りたい方は、こちらの記事もぜひ参考にしてください。
【関連記事】【成功事例付き】サイト導線とは?重要な理由や設計時のポイントを解説
コツ①:デスクトップ用サイト(PC版サイト)では必ず入れる
ポップアップバナーは意外と簡単にできてしまううえ、訴求内容によってはクリックされやすいので、PC版サイトではデフォルトで入れていったほうが良いと思います。
特に、BtoBサイトはおすすめですね。
ただ、スマホ版サイトでは大きくバナーが出ると、わずらわしく感じてしまいそうです。
そうですね。
実際、ポップアップバナーを「×」ボタンで消した割合は、スマホ版サイトで40%〜50%ほどにも上ります。
一方、PC版サイトの取消率は10%以下でした。
ユーザーの利便性を考えると、やはりポップアップバナーはPC版サイトのほうに設置したいですね。
コツ②:引きの強い訴求を盛り込む
では、ポップアップバナーにはどのような内容を掲載すべきでしょうか。
具体的な金額や「無料」など、引きが強い訴求が入っていると良いですね。
ポップアップバナーで視界の端に少しお邪魔しながら情報を出すことを考えると、「Amazonギフト券〇〇円分プレゼント」など、何かしらのお得情報を示したいところです。
「無料サンプル」という訴求は、特に効果的だと思います。
逆に、「資料ダウンロード」は、引きが弱いと感じます。
SEOは潜在層までリーチする分、「資料のダウンロードまでは、まだいらない」というユーザーも多いですからね。
ホワイトペーパーも独自情報が満載だったらまだしも、単なる商品説明では魅力を感じにくいと思います。
セミナーセミナーページの誘客にしても、「今回限りで、こんな話をします」「この方(有名人)と対談します」といったインパクトがあれば、また違ってくるかもしれません。
SEOの過去・現在・未来

SEO対策の過去・現在・未来に関するトピックとして、以下の2つを紹介します。
- 5年前と変わったこと・変わらないこと
- AIがKnowクエリに答える時代へ
それぞれ詳しく見ていきましょう。
5年前と変わったこと・変わらないこと
5年前と今のSEOで、大きく変わったところとかありますか。
冒頭で出たE-E-A-Tやオリジナル情報の重要性は、5年前よりも大きくなっていますね。
また、SEOのベストプラクティスについて、誰でも簡単かつ無料でアクセスできるようになった点も注目ポイントです。
YouTubeや書籍で鉄板の手法を知れる分、そのやり方を淡々と抜け漏れなく行えているかによって、成果も変わってくると思います。
AIがKnowクエリに答える時代へ
検索結果画面の上部にAIの回答内容が表示されるようになりましたが、SEOにはどのような影響があるでしょうか。
「〇〇を知りたい」などKnowクエリと呼ばれるような分野のキーワードは、AIに聞いてしまったほうが早いので代替される可能性が高い、あるいはすでに代替されていると感じます。
一方で、BuyクエリやDoクエリといったコンバージョンに近い分野のキーワードは、SEOのほうがまだ強いといえます。
実際に買った・行った人の評判などは、AIでは代替できない情報です。
生成AIの回答結果ばかりが表示されて検索エンジンを使う方がいなくなってしまうのは、Googleとしても避けたいところでしょう。
だからこそ、今の検索アルゴリズムはE-E-A-Tやオリジナル情報を重視しているのだと思います。
生成AI技術を取り入れた新しい検索エンジンの機能「SGE」の基礎知識やSEOとの違いなどを知りたい方は、こちらの記事もあわせてチェックしてみてください。
【関連記事】GoogleのSGEとは?SEOへの影響や企業が取るべき対策を解説
AI時代で生き残る!これからのSEO戦略

AI時代で生き残るためのSEO戦略として、以下の2つを解説します。
- 対策を強化すべきクエリ
- Knowクエリの対策例
それぞれ詳しく見ていきましょう。
対策を強化すべきクエリ
冒頭でお伝えしたキーワード選定でトップ100を抽出したあと、Knowクエリは抜いたほうが良いのでしょうか。
それとも、Knowクエリに対するコンテンツも作ったうえで、自社ホームページの専門性を高めたほうが効果的ですか。
キーワード単位で見ていくというよりも、記事単位で「オリジナル情報が入っているか」を見たほうが良いかと思います。
検索流入を増やしたい局面であれば、検索ニーズが大きいKnowクエリのキーワードを対策しつつ、独自情報を盛り込むことが大切です。
検索ボリュームが1万以上などであれば、一番上に生成AIの回答が出たとしても、自社のKnowクエリ記事がまったく見られないということはないと思います。
今までより流入が少なくなるとしても、オリジナル性を意識しながらKnowクエリを対策していくということですね。
そうですね。
この部分をSEOコンサルタントと伴走しながらコンテンツに練り込んでいけると、これからのSEOに合ってるかなと思います。
Knowクエリの対策例
例えば、地元の住宅会社さんで「ツーバイフォー(2×4)工法 とは」のようなKnowクエリがあったとします。
このような場合は、ツーバイフォー工法の概要についての回答をAIに任せつつ、その下に上位表示されるようSEO対策したいところです。
具体的には、「ツーバイフォー工法のメリット・デメリット」のような座学部分を記事の冒頭に書いたうえで、以下のようなオリジナル情報を盛り込むということですね。
| ちなみに弊社では、ツーバイフォー工法と〇〇工法の間をとった▢▢工法(オリジナル情報)を採用しています。ツーバイフォー工法のメリットを上手く活かしつつ、△△という独自のやり方(オリジナル情報)で♢♢を実現し、デメリットを打消しているのです。 |
そうですね。
実際の写真や動画を挿入したり、独自の考え方みたいなところを組み込んだりすると、オリジナル性がより増して良いと思います。
【余談】SEOはここが難しい

最後に、SEO対策ならではの難しさについて、以下の2つを紹介します。
- 専門的なキーワードの洗い出し
- ニッチキーワードへのアプローチ
それぞれ詳しく見ていきましょう。
専門的なキーワードの洗い出し
日々SEOコンテンツに携わっていて、「ここが悩ましいんだよな」ってところはありますか。
SEO支援に携わっているなかで難しく感じるのは、専門的なキーワードの洗い出しです。
ツールを使ったり、頭の中で考えたりすることで出せるキーワードはありますが、やはりクライアント理解や専門知識がないと出てこないキーワードも必ずあります。
また、同じ事象でも違う角度から考えると出てくるキーワードもあって、他社さんでどうしているか結構気になるところですね。
キーワードについて、クライアントからどれだけ深く傾聴できるかが大切になってきそうです。
そこはどうしても、属人的に進めないといけない部分ですね。
そうですね。
だからこそ、きちんと取り組めば成果がより上がりやすくなり、SEO支援の価値も大きくなると思います。
ニッチキーワードへのアプローチ
例えば、リフォームを請け負っている住宅会社があったとします。
しかし、「リフォーム」というキーワードは「リノベーション」と組まないと、検索ボリュームがまったく出ません。
このように、ニッチで検索ボリュームが足りないキーワードへの対策はどうしたら良いでしょうか。
事業として行っていなかったとしても、集客用のキーワードとして「リノベーション(リノベ)」も対策します。
どれだけ良いコンテンツやクリエイティブを作っても、見られなかったら意味がないためです。
「リノベーション(リノベ)」と検索している方の中にも、リフォームの需要が含まれている可能性も十分考えられますものね。
そうですね。
あくまでも集客用のキーワードであることをクライアントに理解いただいたうえで、SEO対策を進めていけたらと考えています。
まとめ:SEOで成果を上げるためにはノウハウが必須

近年では生成AI技術も発展してきており、単にコンテンツを作るだけではSEO対策の成功は望めません。
成果を上げるためにはE-E-A-Tやオリジナル情報の重要性を理解し、キーワード選定などのノウハウを身に付ける必要があります。
なお、弊社は月額5万円から始められるSEO対策サポートサービスを展開しております。
Webサイト運用やWeb広告などSEO対策と同時に進めることで集客力を上げる施策も、プロが支援いたします。
自社ホームページを通じて売上を拡大させたい方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。
【関連記事】コーポレートサイトのSEO対策とは?主な方法や成功事例を解説!
【関連記事】SEOとリスティング広告の違いを5つの観点から解説!上手な使い分け方も
【関連記事】【早見表付き】ホームページとブログの違い|使い分け方や併用の成功事例も
さぁ、ご一緒に
はじめましょう。
具体的なご依頼だけでなく、売り方や集客に関することなど現状の課題についても気軽にご相談ください。