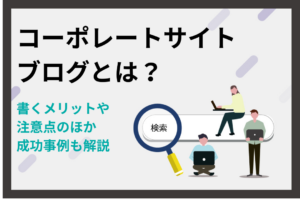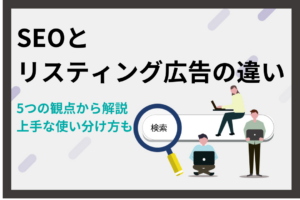-
集客に強いホームページ
-
グラフィックデザイン
グラフィックデザイン -
LINE社認定パートナー事業
-
その他サービス
-
会社案内
-
採用・パートナー募集

自社ホームページの被リンクが増えると、SEO上でさまざまな効果を得られます。
しかし、SEO対策を始めて間もない方からすると、「被リンクは積極的に獲得すべきなのか」「実際にどのように増やせば良いのか」など疑問が多いでしょう。
この記事では弊社の代表取締役「澤田 将司(以下:澤田)」とSEO戦略事業部チームリーダー「加藤 信之(以下:加藤)」の対談をもとに、SEOにおける被リンクの重要性について、昔と今の状況を比較しながら解説します。
良質な被リンクがもたらす効果や具体的な獲得方法もあわせて紹介するので、ぜひ参考にしてください。
目次
【被リンク】昔と今では何が違う?

まずは被リンクを取り巻く状況について、以下の2つを紹介します。
- 重要性は今も昔も変わらない
- より重視する点が異なる
それぞれ詳しく見ていきましょう。
重要性は今も昔も変わらない
SEOの被リンクについて、今と昔で変わったところはありますか。
現代の被リンクも、以前と変わらず重要性は高いと感じています。
Googleの検索エンジンが検索順位をつける1つの要素として被リンクを位置付けているので、今でもかなり大切ですね。
より重視する点が異なる
「昔」を「10年前〜15年前」とすると、現代のSEOは何が違うのでしょうか。
昔で言うところの「ブラックハットSEO」は、どんどん淘汰されていっています。
ブラックハットSEOは被リンクを強制的かつ大量に獲得して、無理やり検索順位を上げる手法です。
しかし、Googleの検索アルゴリズムがアップデートされるごとに通用しなくなりました。
今は、ユーザーにとって役に立つリンクがより重要視される時代になっていますね。
今も昔も被リンクは重要ですが、重視する点が量より質に移行しているということですね。
被リンクとドメイン評価の関係性

被リンクとドメイン評価の関係性について、以下の2つを紹介します。
- 良質な被リンクが多いほどドメイン評価が上がる
- 良質な被リンクはさまざまな効果をもたらす
それぞれ詳しく見ていきましょう。
良質な被リンクが多いほどドメイン評価が上がる
被リンクとドメイン評価(ドメインパワー/ドメインレート※)には、相関性はありますか。
※検索エンジンからの評価を数値化したものであり、高くなるほど上位表示されやすくなる
あると思います。
ただし、単に被リンクが多ければ良いというものではなく、やはり質の高さが重要です。
良質な被リンクとしては、以下のようなケースが挙げられます。
- ドメインパワーが高いホームページからのリンク
- 自社ホームページと関連性が高いホームページからのリンク
- SEO評価の高いページからのリンク
また、ホームページの末端ページよりは、トップページからリンクをもらう方が被リンクの質としては高いと思います。
それは、なぜでしょうか。
SEO評価が上層ページに集約されていくためです。
具体的にはブログ記事を集めたまとめ記事、さらにまとめ記事を集めた常設ページ・トップページなどからの被リンクが理想的です。
ドラゴンボールで言うと、悟空やベジータといった個々のページよりも、それらをまとめたサイヤ人一覧のページはSEO評価が高くなります。
さらには各種族をまとめた最上層のページはSEO評価がより高くなり、そこからリンクをもらえるとドメイン評価が上がりやすいということですね。
そういうことになります。
企業ホームページの基本構成について振り返りたい方は、こちらの記事もぜひ参考にしてください。
【関連記事】企業ホームページの構成で押さえたい8つのポイント!業種別の事例も解説
良質な被リンクはさまざまな効果をもたらす
上記のような良質な被リンクをもらってドメイン評価が上がると、どのような効果が得られるのでしょうか。
自社ホームページのページが上位表示できる可能性が高くなり、検索エンジン経由の流入が増えます。
その結果、お問い合わせや予約といったコンバージョンが増えます。
また、リンク元であるホームページやページ自体のアクセスが多ければ、そこからたどって自社ホームページにユーザーが流れてくることも期待できるでしょう。
どちらかというと、リンク元からの直接流入がメインの効果で、SEO評価の向上と検索経由の流入増加は副次的なものかもしれません。
いずれにせよ、良質な被リンクを得られると二度美味しいといえますね。
なお、流入数を増やすうえで重要なキーワード選定のコツについて知りたい方は、こちらの対談記事もあわせてチェックしてみてください。
【関連記事】SEOはキーワード選定が鍵!コンバージョン率を伸ばすノウハウも紹介
被リンクはどれくらい獲得したら良い?

良質な被リンクをできるだけ多く得られたら良いとは思いますが、KPI化して日常業務に組みこむ場合の目安はどれくらいになるでしょうか。
具体的な数値として出したい場合は、Ahrefs(エイチレフス)などのツールを活用するのがおすすめです。
このようなツールでは、競合ホームページが獲得している被リンクについて調べられます。
例えば、競合が100件の被リンクを獲得してれば、12で割った数(約8か所)を毎月のKPIに落とし込むと良いでしょう。
エイチレフスなどのツールを使えば、自社より上位表示されてる競合の被リンク元も分かります。
競合がどこからリンクを獲得しているのかを把握して、自社ホームページでも最低限押さえる、最終的には超えるよう動くということですね。
そうですね。
自社も同じように被リンクを獲得して初めて、競合と同じスタートラインに並べるという感じかなと思います。
Webサイト運用におけるKPIの重要性や設定項目について知りたい方は、こちらの記事もぜひ参考にしてください。
【関連記事】【事例付き】WebサイトのKPIとは?代表的な設定項目やツリー例も解説
意味のない被リンクとは

SEO対策において意味のない被リンクとはどのようなものか、以下の2つを解説します。
- 関連性が低いページからの被リンク
- 被リンク元によってはSEO評価の向上が少しだけ期待できる
それぞれ詳しく見ていきましょう。
関連性が低いページからの被リンク
被リンクの中で、「これは獲得しても意味がないな」というものはありますか。
先ほど触れたブラックハットSEOはもちろん、被リンクだけを目的として関連性が低いページからリンクを得ても意味がないと感じています。
例えば、弊社ベイスは三重県にあるホームページ制作会社です。
この場合、「三重県 ホームページ 制作」で検索したホームページからリンクをもらうのは、意味がありますよね。
一方で、弊社が制作したネジ工場のコーポレートサイトから被リンクを獲得した場合、SEO上はあまり意味がないということですか。
ほぼ意味がないと思います。
実際に、弊社にも被リンク獲得を目的とした営業メールが届いて、3件〜4件ほど相互リンクを掲載したことがありました。
しかし、弊社と関連性の低いホームページなうえ、末端ページからの被リンクだったので、ドメイン評価はまったく変わりませんでした。
被リンク元によってはSEO評価の向上が少しだけ期待できる
では逆に、弊社の事例紹介ページで工場のコーポレートサイトをリンクした場合、工場側のSEO評価に影響はあるのでしょうか。
そのような場合は、リンクを貼るページのSEO評価によって変わってきます。
ユーザーの検索意図を満たす形で事例コンテンツが作られていて、その中にネジ工場のコーポレートサイトが自然な形でリンクされているのであれば、意味はあるかなと思います。
とはいえ、どうしても関連性は薄いので、効果としては工場側のSEO評価が「多少高まる」程度です。
弊社側にとっても、実績として事例をアピールすることでコンバージョン率向上は期待できます。
しかし、SEO上での直接的な効果はないので、被リンクの獲得先としては優先度が低いということですね。
一昔前は、クライアントのホームページ下部に「Powered by 〇〇(制作会社名)」などリンクしたものですが、今となってはそれもまったく意味がないのでしょうか。
そのページの評価がそれほど高くなければ、意味がありませんね。
被リンクはやはり、「ユーザーにとって役に立つリンクか」を第一の軸として考えるべきだと思います。
コーポレートサイトにおけるSEO対策の必要性や具体的な施策について知りたい方は、こちらの記事もあわせてチェックしてみてください。
【関連記事】コーポレートサイトのSEO対策とは?主な方法や成功事例を解説!
【実践編】被リンクの獲得方法

被リンクの獲得方法は、主に以下の2パターンです。
- 独自情報のコンテンツ化で自然に被リンクを得る
- 他社のホームページへ掲載を依頼する
それぞれ詳しく見ていきましょう。
獲得方法①:独自情報のコンテンツ化で自然に被リンクを得る
自然に被リンクをもらうためには、他社が言及したくなるような情報を出す必要があります。
例えば、自社しか持っていない独自情報・調査データやトレンド情報をコンテンツにするといった方法です。
Web上などで露出して、自然発生的にリンクが増えるパターンですね。
たしかに、弊社のクライアントでもテレビに露出したことで被リンクが急増し、ドメイン評価がグッと上がったケースがありました。
ブランディングの一環として専門性のあるデータを出すことで、SEO対策上も良い効果を得られるということですね。
獲得方法②:他社のホームページへ掲載を依頼する
他社のホームページへ掲載を依頼する場合に押さえておきたいのは、以下の2つです。
- 実際の依頼手順
- 掲載を依頼するメディアの判断基準
それぞれ詳しく見ていきましょう。
実際の依頼手順
実際に実施した方法で言えば、例えば「三重県のホームページ制作会社▢選」といった記事を公開しているメディアに、弊社の掲載を依頼したことがありました。
具体的には弊社の特徴やサービス内容とともに、掲載内容のイメージをお問い合わせフォームからメールで伝えました。
このパターンでは、相手にとっての「掲載する価値」を提示する必要がありますね。
単に、「うちでこういう会社なので、取り上げていただけませんか」とだけ伝えても、「誰だろう」「面倒」と思われそうな気がします。
リンク先でしか得られない情報があると、メディア側としても取り上げる価値は出てきますよね。
そういう意味では、メディア側の気持ちになって掲載を依頼するということも、非常に重要だと思います。
そうですね。
また、メディアの先にいるユーザーにとってメリットがあるかも、大切なポイントになります。
先ほどの「制作会社〇選」のような記事で言うと、自社を掲載してもらうことで同記事の網羅性が高まります。
その結果、ユーザーにとっても、より多くの会社と比較できるメリットが生まれます。
被リンク営業をする際は自社ホームページだけではなく、メディアとユーザーの双方が有益になるよう配慮したいですね。
掲載を依頼するメディアの判断基準
メディアによっては「取り上げても良いですが、5万円かかります」といったところもあります。
被リンク営業の費用対効果を上げるために、掲載を依頼するメディアの判断基準を知りたい方が多いと思います。
やはり、メディア自体の評価が判断軸になってくるのでしょうか。
そのページが実際に見られてるのか、SEO評価が高いのかというところも見たほうが良いですね。
例えば、掲載してもらえたとしても、表示回数(=ページビュー)が月10PVほどとなると、5万円を払う価値は非常に低いと思います。
それだったら、リスティング広告に費用を回したほうが成果は期待できますからね。
よほどドメインランクが高いか、常時一位を取ってるようなホームページでない限りは、金銭的価値よりも、独自情報の提供で掲載価値を示すほうが良さそうです。
【上級編】被リンクが負の遺産になるのを避ける方法

SEO対策を見ていると、被リンクが負の遺産となってSEOを阻害するケースも散見されます。
特に、ブラックハットSEOなどで被リンクを大量に集めていたホームページは、負の遺産がたくさん溜まっているのではないでしょうか。
そうですね。
実際、検索アルゴリズムのアップデートがあるごとに、ドメインランクが乱高下しているという話も聞きます。
しかし、「リンクを外してください」と相手のホームページオーナーに伝えるのは数が多すぎて、現実的ではない気がします。
その場合は、Googleサーチコンソールなどを使って、リンクを否認することが可能です。
すでに獲得しているものを自ら手放す作業なので、かなり勇気が必要そうです。
とはいえ、関連性が低い外国語のホームページだったり、明らかに悪質なサイトだったりするのであれば、迷わずリンクを否認して良いでしょうか。
良いと思います。
低品質の被リンクがないか、半年に1回はチェックしておきたいところです。
弊社も含め、特に社歴が長い会社は確実に実行したいですね。
相当昔に獲得した被リンクの中には、今見ると否認すべきものが含まれている可能性も大いにありそうです。
加えて、中古ドメインを使っている場合も、さまざまな被リンクが付いている可能性があります。
その場合も、どのような被リンクがあるのか、一度見直してもらったほうがいいかなと思います。
まとめ:SEO評価の向上には被リンクの獲得も有効

SEO評価を向上させるためには、被リンクの獲得も重要な施策の1つとなってきます。
しかし、単に量を増やせば良いというものではありません。
自社ホームページと関連性が高く、SEO評価も高い上層ページからの良質な被リンクを狙うことが大切です。
自社が持つ独自情報やトレンド情報を活用し、他社ホームページが言及したくなるコンテンツを制作していきましょう。
なお、弊社は月額5万円から始められるSEO対策サポートサービスを展開しております。
Webサイト運用やWeb広告などSEO対策と同時に進めることで集客力を上げる施策も、プロが支援いたします。
自社ホームページを通じて売上を拡大させたい方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。
【関連記事】【企業様向け】弊社との初回面談時の事前準備ガイド|全体の流れや必要な情報を解説
【関連記事】【事例付き】ホームページ制作後にやるべきWebマーケティングとは?
【関連記事】SEOとリスティング広告の違いを5つの観点から解説!上手な使い分け方も
さぁ、ご一緒に
はじめましょう。
具体的なご依頼だけでなく、売り方や集客に関することなど現状の課題についても気軽にご相談ください。