-
集客に強いホームページ
-
グラフィックデザイン
グラフィックデザイン -
LINE社認定パートナー事業
-
その他サービス
-
会社案内
-
採用・パートナー募集

近年はインバウンドが日本経済に大きな影響をもたらしており、企業としても外国人に対するアプローチが重要です。
中でも中国から訪れる方は非常に多く、2024年における訪日外客数のうち19.1%を占めています。
しかし、実際に中国人へアプローチするとしても、「どのような方法が適しているのかわからない」という方もいるでしょう。
この記事では、中国人に情報を発信する方法として、小紅書(RED)と呼ばれるアプリについて解説します。
他のSNSとの違いや日本企業が活用すべき理由もあわせて紹介するので、ぜひ参考にしてください。
引用:日本政府観光局(JNTO)|訪日外客数 2024年 各国・地域別の内訳
目次
小紅書(RED)とは

REDとはどのようなアプリなのかについて、以下に挙げる3つのポイントから紹介します。
- アプリの特徴
- 中国で人気がある他のSNSとの違い
- 日本企業の活用実態
それぞれ詳しく見ていきましょう。
アプリの特徴
REDとは中国において人気のSNSで、写真や動画とともにさまざまな情報が投稿されているアプリです。
特にグルメやファッション関連の投稿が目立ち、写真・動画がメインであることから「中国版Instagram」とも称されています。
REDの主な機能は、以下の通りです。
- 写真・動画の投稿
- EC販売
- レビュー
- ライブ配信
若い世代の女性ユーザーが最も多く、コスメやファッションなどの流行をREDから仕入れています。
気になる商品があれば、投稿やライブ配信から直接購入に進むことも可能です。
特に、中国の若い女性ユーザーに対して情報を届けたい場合には、REDの運用を視野に入れましょう。
中国で人気がある他のSNSとの違い
中国で人気がある他のSNSとして挙げられるのは、「Weibo」や「WeChat」などです。
Weiboは中国版Twitterとも称され、主に短い文章や写真などの投稿に適しています。
若年層の利用者が多い点はREDと共通していますが、男女のどちらにも利用されているのが異なる点です。
例えば、福山雅治さんや山下智久さんなど、日本の芸能人もWeiboのアカウントを開設し、中国向けに情報を発信しています。
一方、WeChatは中国版LINEと呼ばれ、名前の通りユーザー同士でチャットできるSNSです。
中国では連絡ツールとして幅広く使われており、ユーザー数の多さが特徴になります。
REDは不特定多数のユーザーに対して公に情報を発信するのがメインですが、WeChatではフォロワー個人へのアプローチも可能となっています。
日本企業のREDの活用実態
実際にREDを運用している日本企業・店舗のフォロワーTOP10は、下表の通りです(2024年12月時点)。
|
順位 |
企業・店舗名 |
フォロワー数 |
業種 |
|
1位 |
UNIQLO |
45万9,000人 |
ファッション |
|
2位 |
ドン・キホーテ |
24万3,000人 |
ディスカウントストア |
|
3位 |
マツモトキヨシ |
18万4,000人 |
ドラッグストア |
|
4位 |
Loft |
10万1,000人 |
雑貨店 |
|
5位 |
niko and … |
9万5,000人 |
ファッション |
|
6位 |
東京生活館 |
8万7,000人 |
ドラッグストア |
|
7位 |
スギ薬局 |
7万9,000人 |
ドラッグストア |
|
8位 |
代官山Candy apple |
6万8,000人 |
飲食点 |
|
9位 |
SNIDEL |
6万2,000人 |
ファッション |
|
10位 |
DESCENTE |
6万1,000人 |
スポーツ用品ブランド |
TOP10に入っている中ではドラッグストアが最も多く、次いでファッション関連という結果です。
実際、中国人観光客がドラッグストアなどで、爆買いしている様子を目にした方も多いでしょう。
その背景には、中国人がREDから情報を得ているということも理由の1つとなっています。
なお、弊社ではSNSの運用に長けた専門家が、RED運用代行を実施しています。
REDの運用によってインバウンド集客を成功させたい方は、ぜひお問い合わせください。
日本企業における小紅書(RED)の活用アイデア

日本企業におけるREDの主な活用アイデアは、以下の3つです。
- 越境EC
- 訪日インバウンド対策
- ライブコマース(ライブ配信によるプロモーション・EC販売) など
RED自体にEC機能があるため、新たに中国人向けの販売ページを作成することなく国をこえた取引を実現できます。
投稿やレビューから興味をひくだけでなく、ライブ配信機能を使ったリアルタイムでのプロモーションおよび販売も可能です。
このように、REDで自社の商品・サービスを知り、日本を訪れた際の購入につながる可能性もあります。
中華圏での販路を拡大したい企業も、REDを有効活用すべきといえるでしょう。
日本企業が小紅書(RED)を活用すべき理由とは
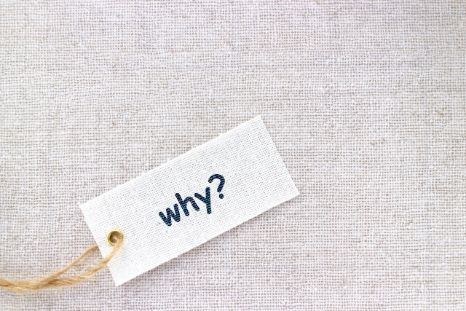
日本企業がREDを活用すべき理由は、中国からでは日本のサイトにアクセスできず、サービスの訴求ができないためです。
中国ではグレートファイヤーウォールの影響により、日本にサーバーがあるサイトは表示されない、もしくは閲覧できたとしても極端に遅くなります。
また、中国大陸向けにWeb上で発信する場合には、中国国内にサーバーの設置が必要です。
ICPライセンス(※)の取得も必要となり、手続きが非常に煩雑で現実的ではありません。
※中国を拠点としてホームページを開設する際の登録手続き
しかし、REDを利用すれば、上記の問題にひっかかることなく、中国大陸向けに情報発信できます。
小紅書(RED)を日本企業が活用する際の注意点

REDを日本企業が活用する際の注意点は、以下の2つです。
- 広告目的の投稿はPR表記が必須となる
- SEOのように上位表示に向けた対策が必要になる
それぞれ詳しく見ていきましょう。
なお、弊社では中国を中心としたデジタルマーケティングの担当者を募集しています。
運用ディレクターとして中国向けのマーケティング施策を行いたい方は、RED運用担当者ページをご参照ください。
注意点①:広告目的の投稿はPR表記が必須となる
広告を目的として投稿する場合には、中国の法律に従いPR表記する必要があります。
近年は日本でも法律に準拠しPRの表記が必要となっていますが、中国でも同様です。
例えば、インフルエンサーを起用してマーケティング施策を行う場合にも広告目的となるため、PR表記を必ず掲載します(※)。
※自社アカウントでの投稿であればPR表記は不要
REDを活用して広告を出す場合には、中国の法律が適用される点も覚えておきましょう。
注意点②:SEOのように上位表示に向けた対策が必要になる
RED内で上位表示させるためには、SEOのような対策が必要です。
上位表示される条件には、以下の5つがあると言われています。
- エンゲージメント率(いいねやコメントシェアなど)
- ユーザーの興味との関連性
- コンテンツの質
- 視覚的な要素
- フォロワー数とユーザーの信頼度
アカウントを開設したとしても、ユーザーに閲覧されなければ効果は見込めません。
RED独自のアルゴリズムを理解するためにも、実際に上位表示されている投稿やアカウントを参考にしましょう。
小紅書(RED)のアカウントを開設する方法

REDのアカウントを開設する方法は、以下の4ステップです。
- 必要情報の準備
- アプリのインストール
- 電話番号の認証
- 基本情報の入力
REDは日本語に対応しておらず、中国語もしくは英語で操作する必要があるため注意してください。
企業アカウントとして運用する場合には、さらに審査を受け、認証バッジを取得します。
まとめ:小紅書(RED)とは中国の女性に人気のSNSアプリ

REDは中国の女性に人気のSNSアプリで、ファッションやコスメなどのプロモーションに効果的です。
自社の商品・サービスを中国に向けて発信したい場合には、REDの運用を始めましょう。
なお、弊社ではREDを活用した中国向けのマーケティング支援として、RED運用代行を行っています。
中国からの集客によって売上向上を目指したい方は、ぜひ弊社までご相談ください。
【関連記事】SNS運用を始める企業は必見!メリット・デメリットや成功事例を解説
【関連記事】売上につながるインスタのビジネスアカウントとは?開設手順や成功事例も
【関連記事】【地方の中小企業様向け】Webマーケティングの始め方ガイド!基本の流れを解説
さぁ、ご一緒に
はじめましょう。
具体的なご依頼だけでなく、売り方や集客に関することなど現状の課題についても気軽にご相談ください。







